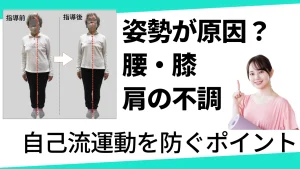プロテインは本当に必要?50代からの筋肉づくりと栄養の話
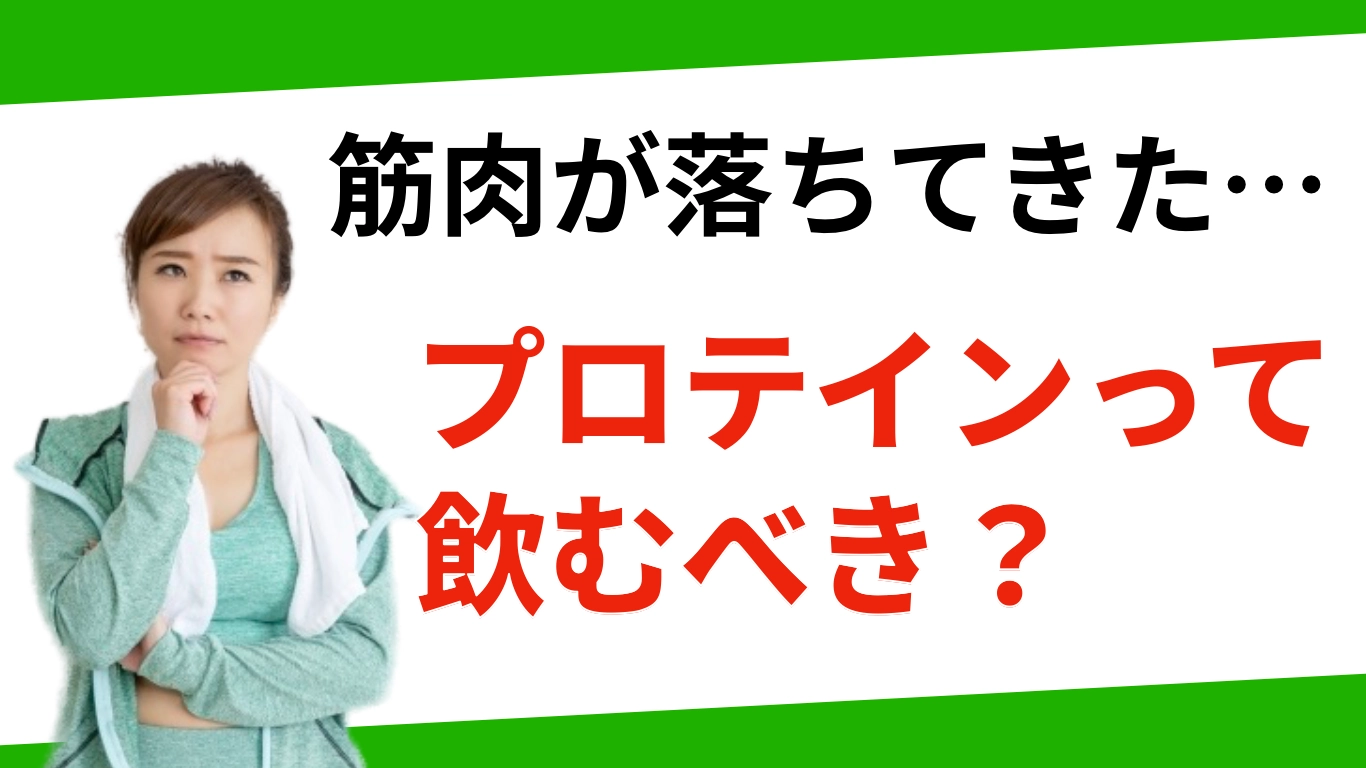
パーソナルトレーナーの小林素明です。
「運動するならプロテインを飲んだほうがいいですよね?」 そんなご相談をよくいただきます。
たしかに、筋肉をつくるには「たんぱく質」が欠かせません。しかし実は、日常の食事だけでも、必要なたんぱく質はしっかり摂れている場合も多いのです。
重要なのは、たんぱく質“だけ”では筋肉づくりがうまくいかないということ。筋肉には他の栄養素、特に糖質とのバランスも深く関係しています。
今回は、
- プロテインは本当に必要なのか?
- たんぱく質の適正量は?
- なぜ「たんぱく質だけ」では不十分なのか?
この3つを、体づくりの視点からわかりやすく解説します。
プロテイン=必ず必要?という誤解

テレビやインターネットでは、運動後にプロテインを飲んでいる場面をよく見かけます。そのため、運動を始めると、「プロテインは飲まないと筋肉がつかない」と考えてしまうのも無理もありません。
結論から言えば、プロテインは「絶対に必要」というものではありません。そもそも「プロテイン」とは、英語で「たんぱく質」のこと。
私たちは毎日の食事から、すでにたんぱく質を摂っています。
たとえば――
- 朝食の納豆と卵
- 昼の焼き魚定食
- 夜の豆腐入りみそ汁と鶏肉炒め
こうした日常の食事にも、しっかりたんぱく質は含まれており、1日3食をバランスよく食べていれば、多くの人は十分な量を摂取している可能性があります。
では、なぜプロテインが注目されているのでしょうか?
サプリメントと食事の違いを知る
その理由は、「手軽にたんぱく質を補える」ことにあります。
- 体調がすぐれず固形物が食べにくいとき
- 食欲が落ちて食事量が減っているとき
- 外出や仕事、家事でゆっくり食事がとれないとき
プロテイン(粉末タイプやドリンク)は便利な補助食品として大変役立ちます。僕自身も、食事が十分に摂れない日があります。そんなときは、プロテイン入りのサプリメントを購入しています。
つまり、プロテインは「食事の代わり」ではなく、「食事で不足するときの補助」と考えるのが良いでしょう。
日本人のたんぱく質摂取量は不足している?

たんぱく質が必要と言われている背景には、高齢になると筋肉量の低下やフレイル(虚弱)のリスクが高まることにあります。
実際に私たちは十分なたんぱく質をとれているのでしょうか?
厚生労働省の「国民健康・栄養調査」(令和元年)によると、60代・70代の多くの方は、1日の推奨量に近い、あるいはそれ以上のたんぱく質をすでに摂取しているケースも少なくありません。
たんぱく質はどれくらい必要?

一般的に、たんぱく質の1日の必要量は「体重1kgあたり約1.0g〜1.2g」が目安です。たとえば、体重60kgの方なら「60g〜72g」が目安になります。
【たんぱく質の目安量(一部)】
- 卵1個:6〜7g
- 納豆1パック:7g前後
- 鶏むね肉(100g):約22g
- 焼き魚(1切れ):15〜20g
- 木綿豆腐(1/2丁):約10g
3食の中で毎回15〜20g前後のたんぱく質がとれていれば、必要量はおおよそクリアできます。
たんぱく質を摂取するときのポイント
たんぱく質ならどんな食品でも良いかと言いますと、そうではありません。
- 動物性食品(魚・肉・卵)
- 植物性食品(大豆製品など)
この2つのたんぱく質をバランスよく取り入れていることが大切です。動物性食品のたんぱく質に偏ると、以下のようなデメリットがあります。
- 脂質やコレステロールの過剰摂取につながり、動脈硬化や心疾患のリスクが高まる。
- 食物繊維が不足し、便秘や腸内環境の悪化を招く。
- ビタミンやミネラルの偏りが起きやすく、疲れやすさや代謝低下の原因になる。
たんぱく質がしっかりとれる!1日の食事モデル【たんぱく質75g摂取】
例:筋トレをしている・体重60kgの方(必要量72〜84g)
| 食事 | メニュー内容 | おおよそのたんぱく質量 |
|---|---|---|
| 朝食 | ・ごはん1杯(150g) ・納豆1パック ・卵1個 ・味噌汁(豆腐入り) |
約20g |
| 昼食 | ・焼き鮭(1切れ 約80g) ・ほうれん草のおひたし ・ごはん1杯 ・味噌汁 |
約25g |
| 夕食 | ・鶏むね肉の野菜炒め(100g) ・冷ややっこ(1/2丁) ・ごはん1杯 ・ゆで卵1個 |
約30g |
| 合計 | 約75g | |
体重60kg/筋トレに励んでいる人の場合、1日合計75g前後を目標。【目標を達成】
ポイント
- 主菜(肉・魚・大豆製品)を1食1品は意識します
- 豆腐・納豆・卵を上手に使えば、無理なく摂取可能です
- ごはんなどの糖質も一緒にとると、吸収効率アップします
たんぱく質だけでは筋肉にならない理由

実はたんぱく質だけを摂っていても、筋肉は効率よく作られません。ここで大事になるのが「糖質」と、その糖質によって分泌されるインスリンというホルモンです。
インスリンは、血糖値を下げるだけでなく、筋肉にたんぱく質を運び入れるサポート役も担っています。そのため、食事で糖質が不足するとインスリンが十分に分泌されず、せっかく摂ったたんぱく質もうまく筋肉に使われません。
特に50代以降は、筋肉が落ちやすくなる年代です。主食(ごはん・パン・麺)をゼロにするのではなく、適量をしっかり摂って、たんぱく質とバランスをとることが大切です。
※ただし、病院で食事指導を受けられている方はこの限りではありません。
食事+プロテインで栄養を補うのは、有効な手段
プロテイン(粉末タイプやドリンク)は便利な補助食品として大変役立つことを話しました。50代以降は食事の量が減り、筋肉が落ちやすくなります。そんなときに食事+プロテインで栄養を補うのは、有効な手段です。
また、運動後30分以内は「筋肉の回復を助けるゴールデンタイム」とも言われ、たんぱく質の吸収がスムーズになります。このタイミングでプロテインを活用するのも、効率的です。
しかし、プロテインを飲めば筋肉がつくわけではありません。日常の食事や運動と組み合わせて使うことが、何よりも大切になります。
合わせて読んでおきたい記事
サプリメントに頼りすぎない体づくりのすすめ

筋肉づくりに必要なのは、たんぱく質だけではありません。最も大切なのは、「食事」「運動」「休養」の三拍子が揃っていることです。
いくら高価なプロテインを飲んでも、運動をしていなければ筋肉への刺激が足りませんし、十分な睡眠や休養がなければ、体が回復・成長できません。
短期間で結果を求めすぎたり、サプリメントにばかり頼ってしまうと、かえって体に負担がかかることもあります。大切なのは、毎日できる範囲で、コツコツと続けること。
- 偏りのない食事を意識する
- 自分に合った運動を取り入れる
- しっかり眠って、体を休める
こうした基本を大事にすることで、年齢に関係なく、少しずつ体は変わっていきます。特に日本人は、睡眠時間が足りていないことが知られています。7〜8時間の睡眠は、確保しておきたいのものです。
合わせて読んでおきたい記事
まとめ/プロテイン神話”に惑わされない、自分に合った選択を
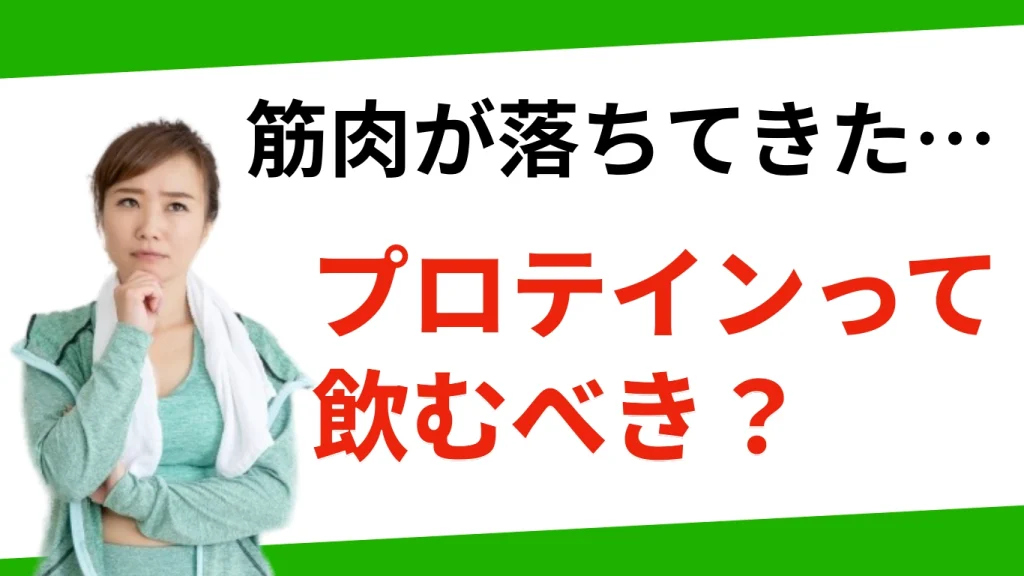
「筋肉づくり=プロテイン」と思われがちですが、必要かどうかは人それぞれです。年齢や活動量、食事内容によっても変わります。
普段の食事でたんぱく質がしっかりとれていれば、プロティンに頼らずとも筋肉は育ちます。
ただ、食が細くなった方や、忙しくて食事が不規則な方には、プロテインが便利な補助になることもあります。
大切なのは、「何を飲むか」よりも、自分の生活の中で何が不足しているのかを知ること。
栄養・運動・休養のバランスを見直し、無理なく続けられる形を整えることが、健康的な筋肉づくりへの第一歩です。
もし運動を始めたいけれど方法がわからない方は、マンツーマンの運動サポートを行う「どこでもフィット」をご利用ください。
30年以上の指導経験とテレビ出演実績を持つトレーナー・小林素明が、目的や体力に合わせた運動を丁寧にサポートします。
運動が初めての方でも安心してご利用いただけます。まずは体験レッスンから始めてみませんか?
参考文献
- 寺田新(2024)「スポーツ栄養学 第2版: 科学の基礎から「なぜ?」にこたえる」東京大学出版会
- ルイーズ・バーク、ヴィッキー・ディーキン(2023)「スポーツ栄養学」大修館書店
- 厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」
フィットネスの始め方を知りたい方へ
当メディア『大阪発!心と体を豊かにするフィットネス・どこでもフィット』では、初心者の方が簡単にフィットネスを始められる方法をご紹介しています。
運動指導歴30年以上、テレビ出演多数、1万レッスン超の実績を持つ小林素明が、専門的な知識と経験を活かして、信頼性の高い情報をお届けします。
これからフィットネスを始めたい方にぴったりの、初心者向けガイド&簡単エクササイズをご覧ください!
この記事を書いた人


小林素明 (お城好きフィットネストレーナー)
指導歴30年超、テレビ番組「ちちんぷいぷい」「大阪ほんわかテレビ」「ten.」などに出演し、専門的でわかりやすい解説が好評のフィットネストレーナー。
健康運動指導士、マッスルコンディショナー、介護予防運動トレーナーの有資格者。
2010年に大阪市でパーソナルフィットネスジム「どこでもフィット」を開業し、これまでに延べ1万回以上のパーソナルトレーニングを実施。特に50代以上の「加齢に負けない体づくり」に定評がある。
医療機関と連携した安全性の高い運動指導、企業・団体向けの腰痛予防や健康経営に関する講演も数多く行い、受講者から「わかりやすい」と高い評価を得ている。
趣味は城巡り、鉄道とグルメの旅、スポーツ観戦、80~90年代のプロレス、書店めぐり、そして焼肉。身体づくりも人生も、楽しみながら続けることを大切にしている。